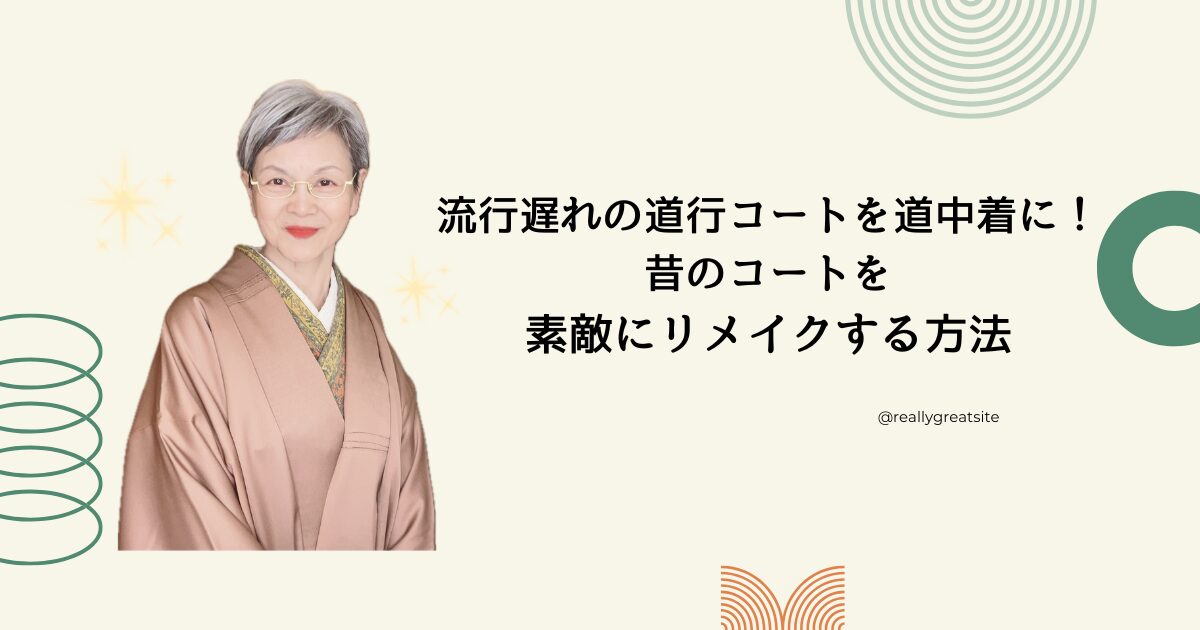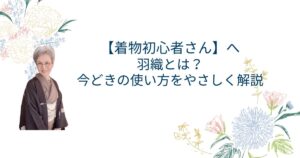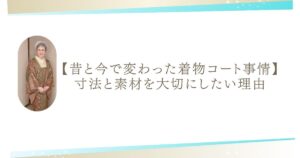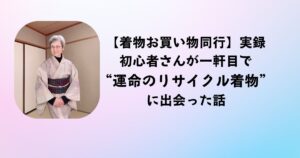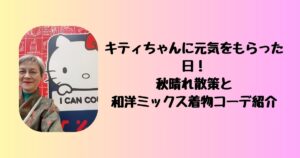嫁入り道具の勿体ないコート
同世代の方々は、嫁入り道具として丈の短い道行コートをお持ちの方が多いと思います。
しかし、今では派手な上に流行遅れで着る機会もほとんどなく、しまいっぱなしになっている方も多いのではないでしょうか。もったいないですよね。
私もそのような経験から、絵羽模様のコートを思い切って色を変え、着丈も長くし、流行遅れの道行コートをある裏技で道中着にリメイクしました!
その方法をお伝えしたいと思いますので、参考にしていただけたら嬉しいです。
一度しか着用せず、長い間タンスにしまっていました。そのため実物の写真はありませんが、近いイメージの画像をAIで作成しました。実物はもう少し明るい印象です。

コートの種類
和装の上着の形には、大きく分けて3つのタイプがあります。
- 道行コート:礼装向きのコート。襟の形が額縁のように角ばっているのが特徴。
- 道中着:外出用のコート。フォーマルからカジュアルまで対応でき襟の合わせ方は着物と同じ。
- 羽織:洋服でいうジャケットやカーディガンのようなもの。室内でも着用可能。
それぞれの上着は、用途や場面に応じて使い分け、和装をより快適に美しく装うために重要な役割を果たします。
絵羽コートとは
絵羽(えば)とは、広げたときに模様が途切れず、模様が全て繋がっているデザインのことです。
柄の付け方によって、コートも礼装や正装に適したもの、カジュアルなもの、お洒落な印象を与えるものなど、さまざまな種類があります。
一回ぐらいしか着用していないので写真が有りませんが、今回の私のコートは絵羽柄で道行き衿でしたのでどちらかというとフォーマルなコートでした。
柄付けには、地模様のみの無地コートの他、主に3つの種類の柄があります。
1. 絵羽模様:コートを広げたときに模様が途切れず、一枚の絵のように模様が繋がっているデザイン。主にフォーマル用。
2. 小紋柄:全体に細かい模様が散りばめられているデザイン。カジュアル向き。
3. 飛び柄:柄と柄の間に広いスペースがあり、模様が飛んでいるデザイン。柄によってはフォーマルにもカジュアルにも対応可能。
左の3枚は若い世代のコートです。赤い色めが定番でした。

コートに適した生地
コートは適した生地で作ることが大切です。
かつて専用の「コート地」が作られていた時代もありましたが、現在ではそのような生地は非常に希少となっています。
以下のような生地が使われることが一般的です。
1. コート専用生地
厚みがあり、しわになりにくく、滑らかに落ちるシルエットが美しい生地です。価格は少し高めですが、その分の価値があります。
2. 小紋用の生地
小紋着物の反物を使用する場合は、コートに適したしっかりとした生地を選びます。
3. 羽織模様やコート用に柄付けされた生地
最初から羽織やコートとして仕上げることを想定し、柄の位置やバランスが美しく見えるようにデザインされた染め柄が特徴の生地です。
4. 洋服用の生地
カシミヤやウールなど、洋服に使われる高品質な素材も着物のコートに適しています。
リメイク(仕立て直し)の経緯
経緯として
仕立て直しの経緯として、
①最初は、着丈を伸ばせるかどうかを検討していました。
コートの着丈を延ばすためには、元の縫製をほどいて再仕立てを行う必要があります。
②その際、せっかく縫い直すのなら、色も新しく染め替えることにしました。
そこで、悉皆屋さんから、
③道行き衿を道中衿に変更してはどうかという提案を受けました。
結果的にコートの丈を延ばす目的から色の染め替えやコートのリメイクも同時に行うことになりましたが、まとめて直しを依頼することで、重複する手間や時間、費用をかなり削減できたと思います。
着物の修理や仕立て直しは、一度にまとめて依頼した方が、個別に行うよりも費用が抑えられることが多いです。
複数の修理や仕立て直しを検討している場合は、一緒に依頼することをおすすめします。
着丈直し
コートの着丈を延ばせるかどうかは、縫い込まれている生地の余裕が重要です。
どこにどれくらい余分な生地があるかを判断するのは難しいため、専門家に相談することをおすすめします。
そこで、いつもお世話になっている悉皆屋さんに、コートの丈を長くできないか相談しました。
確認したところ、縫い込み部分に余裕があることがわかり、可能な限り着丈を延ばしてもらうことにしました。
その上、道中衿にしたほうが着丈を長く伸ばせると聞きました。
コートの着丈をできる限り伸ばしたかったので、この機会に形も変えて、カジュアルにも着られるデザインにするようお願いしました。費用は上乗せにならず、その方がより活用できるコートになると考えたからです。
染め直し
昔ながらの定番色であるえんじ色のコートだったため、この機会に年齢に合った色に染め直すことにしました。
ただ、好みの色を言葉でうまく説明するのが難しかったのです。
コートの染め直しにはいくつか方法があります。
- 濃い色の場合は一度色を抜いてから染めます。
- 薄い色の場合は元の色の上から目指したい色になるよう重ねます。
- ただし、生地によっては縮む可能性があるため、寸法が足りるかどうか事前に確認することが大切です。
今回のコートは、元の色の上から目指す色になるよう色を重ねて染め直しました。
色見本の端切れを見ながら作業を進めるのは、きっととても大変だったと思いますが、熟練した染師さんのおかげで仕上がりました。
手間も費用もかかりましたが、なんと3回も色を重ねていただき、ようやく完成しました。
この一連の作業は何年も前の話です。今となってはそんなエネルギーはもうありません。
当時は若かったからこそできたことですね。今思うと、少し疲れる作業でした。
染め替えても江戸小紋の柄がちりばめられて浮き上がっています。

道中着に仕立て直し
繰り返しになりますが、
馴染みの悉皆屋さんに、染め替えるついでに、道行衿(額縁)コートをフォーマルからカジュアルまで対応できる道中着衿(着物衿)コートに仕立て直す方法を提案してもらいました。
着物のほどいた生地をうまく配置することで道行衿コートにするよりも着丈を長く伸ばすこともできました。
思いがけず、うれしい話でした。
通常、道行衿コートを道中着に仕立て直すのは、襟部分の生地が足りないため難しいとされています。しかし、悉皆屋さんが特別な裏技を提案してくれたので、その方法を使って仕立て直してもらうことにしました。
その裏技とは、短い襟を継ぎ合わせ、その継ぎ目にタック(ひだ)を数本取ることで、継ぎ目を目立たなくする方法です。
写真の衿の下前と上前の2箇所に継ぎ目のタックがあります。正直、全く気にならないとは言えませんが、
しっかりした生地の年相応のコートとして蘇ったので、気にせず愛用しています。

コート着丈もこれくらいなら流行遅れには見えません。

染め替えた後も江戸小紋の細かな柄が浮かび上がり、絵羽模様もしっかり残っています。無地よりも上品で格がありながら、カジュアルな場面でも気軽に着られる一枚になりました。

この本にはいろんなお手入れのことが載っていて勉強になります。
たかはしきもの工房https://www.kimonokoubou.co.jp/
まとめ
①最初は、着丈を伸ばせるかどうかを検討
②その際、せっかく縫い直すのなら、色も新しく染め替えることに
③道行き衿を道中衿に変更してはどうかという提案
この③つを同時に行って昔のコートを素敵にリメイクすることができました。
しかし、箪笥の中で眠っていたコートを手間暇かけてよみがえらせるのは、とてもエネルギーが必要です。
それでも、一から新しく作るよりは費用を抑えられ、もともとコート用の生地なので、しわになりにくいのも魅力です。
さらに、他のコートと色がかぶらないので、今ではお気に入りの1着になりました。
色は、自分の好みに合った色無地の残布を持参し、それを色見本として使いました。
染め替えをする場合は、端切れでも構わないので、具体的な色見本があると希望がはっきり伝わります。
悉皆屋さんが用意してくれる色見本はサイズが小さすぎるため、イメージと違う仕上がりになる可能性が高いです。
実際に、私も以前思うような色に仕上がらなかった経験があります。
悉皆屋さんがLINEを使って染め上がりの色を送ってくれますが、スマホの画面越しでは正確な色味を確認することはできません。
そのため、染め上がった後は少し手間でも、悉皆店へ足を運んで確認するのがおすすめです。
確かに、この作業は大変で疲れることもあります。
でも、コートを羽織るたびに「手間をかけて直して本当によかった」と思い、着物好きだった母の顔が自然と浮かびます。
あきらめずに取り組むことで、心穏やかな日々を送ることができています。
読者のみなさんも大切な思い出のコートをお持ちでれば、ぜひ染め替えを検討してみてください。
その際は、必ず見積もりを取ってください。
年齢とともに断捨離をしましたが、名物女将さんの著書を参考にして、古い着物を活かす方法を学んでいます。
たかはしきもの工房https://www.kimonokoubou.co.jp/
最後まで読んでいただきありがとうございます。この記事がお役に立てれば幸いです。
着付け教室も開校しています。着付けや着物リメイクのお問い合わせなどお待ちしております。