 質問者さん
質問者さんこれから、どんな着物を買えばいいのかしら?
年齢に合った着物を楽しみたいけれど60代からは、あまり数を増やしたくないのよね。



最近、着物を楽しみ始めた60代の知人に聞かれました。
きちんと考えて着物選びをするかどうかで、これからの着物ライフが大きく変わります。趣味とはいえ、無駄なく賢く楽しみたいですね。



着物初心者の40代の私たちにも参考になりそう!
ただでさえ高価な着物で損をしたくないもの。



母親の着物で始めたけど、購入となるとハードルが高いわね。ちゃんと理解できるかしら?



まきさんやまりさんは、着付けを始めたばかりだから「着物はたくさん持っていた方がいい」と思うかもしれません。でも本当は、手入れや将来の整理を考えると、枚数を絞って上手に着回すことが大切です。
私も30年以上着物に関わってきて、「もっと早く気づけばよかった」と感じることが多くあります。だからこそ、その経験を皆さんにお伝えしたいと思います。
この記事は、60代向けですが、これからコスパよく着物を揃えたい若い方にも役立つ内容です。
必要以上に購入する必要はありませんが、何を買おうか迷っている方はぜひ参考にしてください。
おすすめは単衣(ひとえ)のお召(おめし)



“おすすめは単衣(ひとえ)のお召(おめし)です”って言われても……それってどういう着物なの? わたしにも合うの?



着付けを習い始めたまきさんのような人のために、
単衣のお召について、わかりやすくご紹介しますね。
単衣のお召・基本のき
着用できる時期
① 裏地がある着物(袷)…10月〜5月に着用します。
② 裏地がなく、袷と同じくらいの厚さの生地、または透け感の少ない薄手の着物…6月・9月に適しています。
③ 裏地がなく、透け感の強い薄手の着物(絽や紗など)…7月・8月に着用します。
ここでおすすめしている「単衣のお召」は、②の「透け感の少ない薄手の着物」にあたります。
なお、③のように透け感の強い生地であっても、着ていて涼しいとは限りません。
透けて見える=見た目は涼しそうですが、着ていて涼しい、とは必ずしも言えないのです。
暑さの感じ方は人それぞれですので、無理せず、自分にとって快適な着こなしを選ぶことが大前提ですが、
近年は温暖化の影響で、TPOに厳密な決まりがなければ、単衣は5月から10月までの約半年間着られるようになっています。
着用できる場面
そのうえ、長い着用期間だけでなく、使い勝手の良さという大きな魅力もあります。
お召とは、先に染めた糸で柄を織り出す着物で、織りの着物の中では最も染めの着物に近い、やわらかく上品な雰囲気があります。ほどよいシャリ感があり、見た目にも涼やかです。
染めの着物では改まりすぎる、紬(つむぎ)ではややカジュアルすぎる――そんな場面にも対応できる、ちょうどよいバランスの一枚です。
おすすめ理由
- 透け感が少ないものを選べば、初夏から初秋まで3シーズン着用できる。
- お召はセミフォーマルからカジュアルシーンまで対応範囲が広い。
- 着付けがしやすく、皺になりにくい扱いやすい着物です。
- 比較的リーズナブルな割に見栄えが良い着物です。
このような理由からコストパフォーマンスの良い着物といえ、着物を増やしたくないけれども一枚買うとしたら、単衣のお召がおすすめです。
ベージュ系の透け感の少ない夏生地のお召は、カジュアルからフォーマルまでさまざまなシーンで着用でき重宝です。透け感が強すぎると着用時期が真夏のみになるのでお勧めできません。購入の際は必ず実際に顔に当てて似合うかどうか判断してください。あくまでも色柄の参考になさってください。
60代の無地お召に合う帯を選ぶときは、実際に着物に当てて、じっくり検討するのがおすすめです。白っぽい帯と濃い色の帯を1本ずつ持っておくと、知的でエレガントな印象になり、とても便利です。
単衣のお召しに夏帯。帯や小物を初夏バージョン、初秋バージョンに変えると半年間着用できます。




おすすめの着物ランキング



私が「使い勝手がよい」と感じている着物は、他にもいくつかあります。
今回ご紹介した無地のお召と比べてどう違うのかも、わかりやすくお伝えしますね。
1位:無地のお召(おめし)
▶ 控えめで上品な光沢、体に馴染みやすく、帯合わせでカジュアルからセミフォーマルまで幅広く対応。着付けもしやすく、長く愛用できます。
2位:色無地(いろむじ)
▶ 一つ紋を入れれば略礼装にもなる万能着物。淡い色から深い色まで年齢や雰囲気に合う色が選びやすく、帯で印象を変えられるのも魅力。ただし、着付けが難しく、季節も限られます。
3位:江戸小紋(えどこもん)
▶ 遠目には無地に見える細かな柄。シンプルながら品格があり、TPOを選ばず着用できます。紋を入れれば準礼装にも。ただし、着付けが難しく、季節も限られます。
このようにやはりお召が一番です。



とても便利そうだけど、良いところもあれば気になる点もあるのかしら?



はい、実はその通りなんです。前にも少し書きましたが、改めて両方お伝えしますね。
メリット
着用期間が広い
透け感の少ない生地を選べば、暑さの厳しい近年は半年間の長い期間活躍してくれます。下に合わせる襦袢も体感温度に合わせて単衣襦袢から夏襦袢まで調整可能で快適に過ごせます。
実際、私は透け感の少ない単衣のお召に(一般的に単衣の下は夏襦袢を合わせます)、単衣襦袢を合わせて4月にも出かけましたが、全く問題なく快適に過ごせました。
対応範囲が広い
無地のお召は帯や小物で季節感や個性も演出しやすいのが魅力です。TPOに合わせやすく、40代からの年齢や好みに左右されず長く楽しめる一枚です。
価格がリーズナブル
無地のお召は比較的手頃な価格で手に入れやすく、高価でなくても、自分に似合う一枚を選べば満足感も得られます。
着付けがしやすい
お召は適度な張りがあって滑りにくく、着付けがしやすい上に染めの着物のような柔らかさもあり、美しいシルエットが作れます。こうした特性から、着付け教室では初心者にお召が勧められることも多く、その着付けやすさが実感されています。
デメリット
お召は雨に弱い
お召は「強撚糸(きょうねんし)」という強く撚りをかけた糸で織られています。この糸は水分を含むと、撚りの力で大きく縮む性質があります。 雨や湿気で濡れると、生地が部分的に縮んだり、表地と裏地の縮み方が違って裾がたわむなどのトラブルが起きやすくなります。
防縮加工や撥水加工をしていないお召は、特に雨の日には避けた方が安全です。
糸がひっかりやすい
お召糸は表面に凹凸やシャリ感が出やすい特徴があります。
この凹凸やシャリ感によって、バッグの金具やアクセサリー、家具の角などの突起物に生地が擦れると、糸が引っかかりやすくなります。つまり、お召の独特な織りと糸の性質が、糸の引き連れやすさの主な原因です。
放置すると被害が広がるため、見つけたらすぐお直しのプロに依頼し補修しましょう。
生地がやや厚めで少し重く感じる
• 糸の量が多い
お召はしっかりとした織り方で、たくさんの絹糸を使っているため、生地自体が厚くなり、その分重さも増します。
• 織り方の特徴
経糸(たていと)の密度が高く、緯糸(よこいと)も強撚糸を使っているので、コシがあり生地がしっかりしているため、厚みや重みを感じやすいです。
• 表面の凹凸(しぼ)
生地表面に細かい「しぼ(凹凸)」があることで、触ったときに厚みや重みを感じやすくなります。
このような糸の使い方と織りの工夫が、お召特有のやや厚めで重みのある質感の理由です。



デメリットはガード加工や丁寧な取り扱いで十分カバーでき、単衣仕立てにすると軽く、着心地に大きく影響することは少ないため、工夫次第で快適に楽しめます。これはお召に限らず、全ての着物に共通して言えることです。自分が納得できる範囲で考えてください。



お召ってあまりなじみがなかったけど、扱いやすそうね。



お召の着物をあまり販売対象にしないのは、コスパが良く長持ちするため、店側にとっては売り替えの機会が少ないからです。加えて、華やかさでアピールしにくく、初心者には地味に見えがちな点もあります。
つまり、お召は品質が良く長く着られる分、販売店としてはあまり積極的にすすめにくい着物という側面があります。



みつ子先生の説明で少しは理解できそうだけど、そんな着物が箪笥にあるかしら・・・でも、なぜ、単衣なの?



良いところに気づきましたね!
単衣の着物を着る季節は基本的に6月と9月ですが、温暖化の影響で実際、茶道の裏千家でも5月から単衣に切り替えることが推奨されています。
また、織りの着物は糸の間に隙間ができやすく、空気が通りやすいので、真夏でも比較的涼しく着ることができます。最近は、気温や体感に合わせて自由に単衣を着る傾向が強まっており、カジュアルな場面では特に、暦にとらわれず自分の快適さを優先して選ぶ人が多いです。
もちろん、盛夏の礼装などには向きませんが、日常のお出かけやカジュアルな場面なら無理なく楽しめるのです。



でも、いざ探すとなると…どこで見つければいいのかしら?



最近は、まず着物専門店よりデパートの呉服売場をのぞくのがおすすめです。洋服感覚で楽しみながら無地のお召などを見ていくうちに、自然と目が慣れ知識も身につきます。
知識をつけてから選んでも、まったく遅くありません。
コーディネート例
単衣のお召とオールシーズン帯
単衣のお召にオールシーズン使える帯を合わせて5月から9月の装いを楽しみます。羽織もお召の単衣です。


このお召は織柄が特徴で、仕立ての際に袖や背縫いの箇所の柄を合わせてもらいました。そのため、帯を袋帯に変えれば附下(つけさげ)としても着用できる一着です。


単衣の「結城縮」と比べると
単衣の「結城縮」(紬)は、上記のお召の10倍の価格です。ただし、軽くて柔らかく、体にしっかり馴染むため、その価値は十分にあります。ただし、着用できるのはカジュアルな場面に限られるので、お召のようにコストパフォーマンが高いとは言えません。


透け感の少ないお召に夏名古屋帯
カジュアルなシーンから少し改まった席までOKの6月〜8月の装いです。
このお召は無地に近い天目染めという細かい不揃いの点の染が入っていて織地もくせがなく帯合わせによってお悔やみまで使えます。


2023年7月に織り柄入のお召とオールシーズン名古屋帯で旅行に行きました。長時間座っていても、シワになりにくくとても助かりました。


メーカーによると、このお召しは真冬以外なら着用可能とのことです。4月にも着てみて、その着心地をお伝えしようと思います。
実際に2024年4月に着て見たところ、見た目に違和感もなく、4月から長く着用できる着物だと実感しました。 10月にも再度着て、記事に追加します。
ただ、4月は朝晩が少し冷えるので、袷の羽織を着ると安心ですね。


たどり着いた結論
あまり数を増やさず、着物ライフを楽しみたい方にはコスパの良い単衣の無地のお召しがおすすめです。特に、
① 透け感の少ないお召しなら、着用できる期間が長くてさらに便利です。
有名なお召しのメーカーさんによると、『毎日着物でお仕事される京都の女将さん達にも大人気』だそうです。
その理由としては、
② 帯合わせがしやすく、着付けが簡単で、お値段以上に見栄えが良いことが挙げられています。
まさに着物上級者にも認められた着物です。
週3回着物を着る私も、最もよく手に取るのは無地のお召しです。着付けや帯合わせが簡単で、仕事前の準備にかかる時間が短縮できるからです。
そして、
③ 長時間座ってもシワになりにくく、着物ハンガーにかけておくと、翌朝には元通りになることもあり、メンテナンスも簡単です。



確かに、一着作るなら単衣のお召しが良さそうね。手持ちの締めたい帯に合いそうな色を探そうかしら。
そんなふうに考えるとどんな着物を買うべきか見えてきたわ〜。



着付けだけでなくお手入れや維持の手間も、年を取るとできるだけ減らしたくなります。
無地のお召しにオールシーズン対応の帯を合わせて、今の時代に合った、モダンでコスパの良い着物ライフを楽しみましょう。



これから、着物を購入しようとしている40代の私達にもお召のコスパ良さは当てはまるわね!
着物はシックでも、帯や小物次第で幅広い年齢層に対応できるのも有り難いわ。



若い人も友人の結婚式や披露宴にドレスではなく着物で出席できれば、洋服のように流行を追わずに済み賢い選択になるわね。
そんな時は、無地のお召しに華やかな洒落袋帯を合わせ、コットンパールの帯留めでエレガントに仕上げればバッチリね!
実際、40代の生徒さんのコーディネートをお手伝いしたとき、本物のパールよりも軽くて今風なコットンパールをおすすめしたところ、素敵に仕上がりとても喜んでいただけました。
【40代から60代までお召の現代的な楽しみ方】
お召は今の暮らしにもなじむ、上質で頼もしい着物です。
なかでも無地の単衣お召は、季節をまたいで着やすく、帯合わせ次第でフォーマルにも普段着にも楽しめます。
高価なものでなくても、コーディネートと着付けの美しさで上品に見せることができます。
個性の強すぎない帯や小物を合わせれば、全体がすっきりまとまり、洗練された印象に。
洋服感覚で色を選べば、統一感が生まれ、年齢を重ねた今だからこそ似合う“現代的な着こなし”になります。
色柄の参考にして、購入の際は必ず顔映りや合わせたい着物と合うかをじっくり検討してください。
普段着からフォーマルまで使える、軽くて上品なコットンパールの帯留めは、三分紐を替えることで様々なシーンで活躍します。
基本的に、小物は薄い色のほうがフォーマルな印象になります。帯留めは金具の大きさで三分紐しか通らない場合もあるので注意してください。
訪問着や色無地、無地お召に合うフォーマル用の帯揚げと帯締めのセットを一組揃えておくと迷わず便利です。
60代からなら暗い色目より顔周りを明るくする華やかな色目をおすすめします。




最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が参考になれば幸いです。
また、着付け教室も開校していますので、ご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。
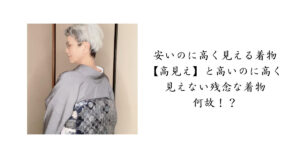
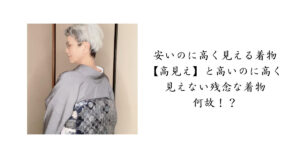
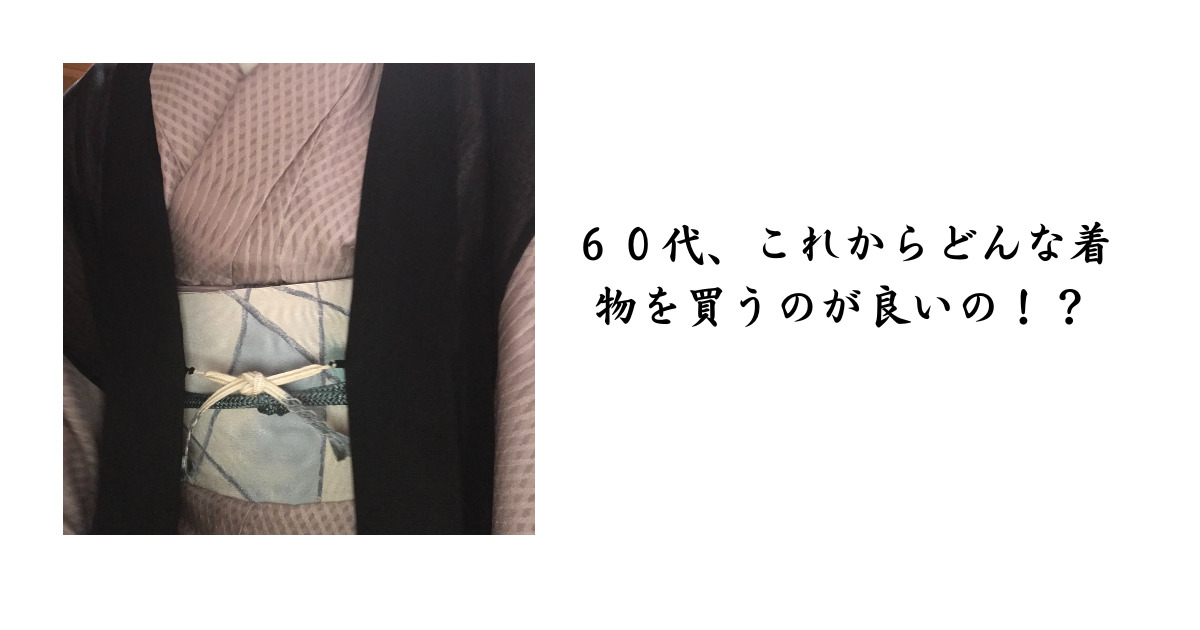
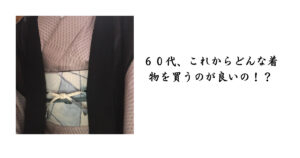

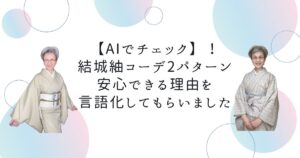



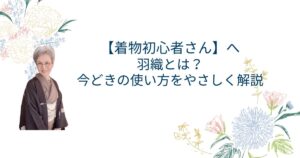
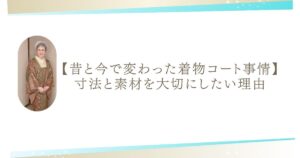
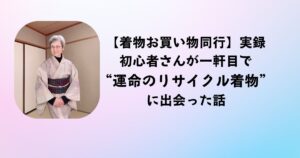
コメント