七五三はお子さんの成長を祝う大切な行事で、受け継がれた着物には家族の絆を深める意味もあります。でも、「着物がちゃんと着られるか不安」「母も着物を着たいけど準備はどうすれば?」など、迷うことも多いですよね。
今回は、七五三の準備スケジュールと、受け継いだ着物を活かすポイントを分かりやすくご紹介します。家族みんなが笑顔で迎えられるよう、ぜひ参考にしてください。
結論
いつから準備を始める?
七五三の準備は早めに開始:6ヶ月前頃からの準備がおすすめ!
① 着物や小物の状態とサイズ確認:シミやサイズ調整が必要なら早めに手配
② 撮影・お参りの予約:2ヶ月前から準備を整え、予約を確定
代々の着物を活かすポイント
③ 試着と確認:1ヶ月前に試着して最終確認を行い、当日安心
④ お母さんの着物を着る場合:小物のアレンジで現代風に仕上げる
⑤ プロの力を借りる:着付けヘアメイクの専門家に相談して安心
また、七五三は「家族でのお祝い」として、親戚や近しい人たちとの食事会もセットになる場合は、スケジュール調整など、その準備も考えておくと良いでしょう。
1. 七五三の基本スケジュール(季節と時期)
七五三は、一般的には10月中旬〜11月中旬の間に行われます。
この時期に合わせて、写真撮影やお参りを計画するのが一般的です。特に、写真撮影を別日にもスタジオなどで行う場合は、お参りのタイミングを家族と相談し、最適な日程を決めましょう。
2. いつから準備を始める?【目安スケジュール付き】
七五三の準備は、早めに始めるほど安心です。ここでは、おすすめのスケジュールを月別にご紹介します。
☆半年〜3か月前(春〜初夏)
• 着物の準備と状態チェック:代々受け継がれてきた着物を使う場合、まずはその状態を確認します。シミや傷、サイズ感などをチェックして、必要ならサイズ調整やお手入れを検討しましょう。
• 部分直しや仕立て直しの検討:着物のサイズが合わない場合は、専門家に仕立て直しを依頼することができます。肩上げや腰上げが必要になることもあります。
男児の羽織は裄がピッタリでも必ず肩上げをしてください。
• 着付けの予約:着物を着るためには、着付け師にお願いすることも考えましょう。事前にリサーチしておくと安心です。
以下、年齢別着物リストです。
7歳女児の着物準備リスト
基本アイテム
• 四つ身の着物• 帯(作り帯または結び帯)
• 長襦袢(半衿付き)• 肌襦袢または肌着
• 腰ひも(多めに見て、作り帯なら4〜5本、手結び帯なら6〜7本)
• 伊達締め
• 帯揚げ
• 帯締め
• しごき
• 帯板
• 子ども用帯枕(作り帯の場合は不要)
• 三重紐(作り帯の場合は不要)
• コーリンベルト(または腰ひもで代用可)
• 足袋
• 草履
• 箱迫(はこせこ)
• びらかん(飾り)
• 扇子(末広)
• バッグ
• 髪飾り
• 薄手のタオル(2〜3枚、補正用)
あると便利なもの
• フェイスタオル(補正用)
• 着物クリップや洗濯ばさみ(トイレや着付け時に便利)
• 雨具(ポンチョ・風呂敷など)
• 着替え(移動や食事後用)
• 大判ハンカチ・バスタオル(食事時の汚れ防止)
• 絆創膏や小さなお菓子(鼻緒ずれや待ち時間対策)
ポイント
• 3歳の着物セットとは小物が異なります。帯や箱迫など7歳用のアイテムが必要です。
• 着物や小物は事前にすべてタグを外し、まとめて持参しましょう。
忘れ物がないよう、リストで一つずつ確認すると安心です。


• 四つ身の着物• 帯(作り帯または結び帯)
• 長襦袢(半衿付き)• 肌襦袢または肌着
• 腰ひも(作り帯なら4〜5本、手結び帯なら6〜7本)
• 伊達締め
• 帯揚げ
• 帯締め
• しごき
• あれば帯板
• 子ども用帯枕(作り帯の場合は不要)
• 三重紐(作り帯の場合は不要)
• コーリンベルト(または腰ひもで代用可)
• 足袋
• 草履
• 箱迫(はこせこ)
• びらかん(飾り)
• 扇子(末広)
• バッグ
3歳女児の着物準備リスト
基本アイテム
• 着物(三つ身)
• 被布(ベスト状の上着)
• 長襦袢(半衿付き)
• 肌襦袢またはインナー(和装用肌着やTシャツでも可)
• 腰紐(2~4本程度、着物に縫い付けがあれば少なくてOK)
• へこ帯(なくても可、被布の下に結ぶやわらかい帯)
• 足袋
• 草履
小物・アクセサリー
• 巾着や和装バッグ
• 髪飾り
• 半衿(長襦袢に縫い付けておく)
• 薄手のタオル(体型補正用、1~2枚)
あると便利なもの
• 替えの靴(移動用)
• 着物クリップ(小)なければ洗濯バサミ(着崩れ防止)
• ソックス足袋(履きやすさ重視の場合)
ポイント
• 3歳女児は「被布スタイル」が主流で、帯を結ばず被布を羽織るため、着付けも簡単で苦しくなりにくいです。
男児(5歳)の羽織袴準備リスト
基本の衣装
• 着物
• 羽織(+羽織紐)
• 袴
• 長襦袢(半衿付き)
• 角帯(袴帯)
• 腰紐(2~3本)
• 肌襦袢または肌着
小物類
• 足袋
• 草履または雪駄
• 扇子(末広)
• 懐剣(かいけん)
• お守り
あると便利なもの
• 靴と靴下(移動用)
• 着替え
• 絆創膏
• クリップや洗濯ばさみ(トイレ時)
• タオル(大きめ)
• 飲み物用ストローやウェットティッシュ
• お菓子や飲み物(気分転換やぐずり対策)
ポイント
• 羽織・袴・着物の3点が基本セットです。
• 半衿は長襦袢に縫い付けておくとよいです。
• 肩上げ・腰上げは事前に済ませておきましょう。裄がピッタリでも必ず肩上げはしてください。男児の羽織の肩上げは必須であり、七五三の準備で忘れずに行うべきです。
• 小物は意味があるので、忘れずに用意しましょう。
このリストをもとに、忘れ物がないかチェックして準備を進めてください。

肩上げには「これから成長する」という縁起の良い意味も込められており、13歳までは肩上げをするのが一般的です。
羽織も着物と同様に肩上げをして、寸法に合わせて調整することが推奨されています。
簡単な肩上げは自宅でも針と糸ででき、撮影やお参りの1日だけの使用なら簡易的な方法でも問題ありませんが、正式には呉服店などでプロに依頼するのが安心です。長襦袢も同様に肩上げが必要です。
男児(3歳)の準備リスト
3歳男児も羽織袴を着ることはできます。
• 3歳は「被布」が主流ですが、羽織袴を着せる家庭も増えています。
• 3歳用の羽織袴は5歳用より小さく、帯や袴の締め付けを避けるため兵児帯や付け紐のみの場合もあります。
• 小物類(足袋・草履・懐剣・扇子など)はほぼ共通です。
まとめ
• 3歳も羽織袴を着せるなら、5歳とほぼ同じ準備リストでOKですが、被布着物や簡易な帯など年齢に合わせて調整するのが一般的です。
七五三のお母さんの着物準備リスト
• 着物(訪問着、付け下げ、色無地が一般的)
• 帯• 帯締め• 帯揚げ• 長襦袢(半衿付き)• 肌着(きものスリップ)• 帯板• 帯枕
• 伊達締め2本• 腰紐4~5本• 衿芯• 補正用タオル(3枚ほど)
• 草履• 足袋• バッグ(必要に応じてサブバッグも)
• 重ね衿(取り入れても無くてもOK)
• 髪飾り(必要に応じて)
プロに任せる場合は事前に着付け店の持ち物リストを確認してください。
あると便利な持ち物・ポイント
• 大判ハンカチやタオル(汗や汚れ対策)
• クリップ(トイレ時の裾留め用)
• あれば、祝儀扇(末広)
• 季節や天候に合わせて防寒具や日傘
• 写真映えを意識したヘアセットやメイク
☆2か月前(晩夏〜初秋)
• 小物の準備:帯、足袋、草履、髪飾りなどの小物を揃えましょう。特に草履や足袋は、事前に試着してサイズが合っているか確認しておくと当日安心です。ストレッチ足袋が便利です。
• 撮影・お参りの予約:写真スタジオでの撮影を予定している場合、希望の日程で予約を入れておくと良いでしょう。参拝の日時も決めて、家族全員の予定を調整しておきましょう。
☆1か月前〜直前
• 試着と確認:着物がきちんと体に合っているか、試着して確認します。特にお子さんは成長が早いので、サイズ感を再チェックしておきましょう。
• 当日の準備:天気予報を確認し、当日の動き方やタイムスケジュールを再確認します。また、お母さんの着物についても最終チェックを行い、すべての準備が整っているか確認します。
3. 受け継いだ着物を着るために気をつけたいポイント
代々受け継がれた着物を着る際には、以下のポイントを押さえておくと安心です。
• シミや傷の確認:長年保管されていた着物には、シミや傷がついていることがあります。専門のクリーニングや修復をお願いすることを検討しましょう。
• サイズの調整:お子さんの成長に合わせて、肩上げや腰上げを行い、着物のサイズ調整をすることができます。
• 小物のアレンジ:伝統的な着物に現代風の小物を合わせることで、より華やかな印象を与えることができます。
4. お母さんの「母の着物」を着る場合のコーディネートのコツ
お母さんの着物を着る場合、次のポイントを考慮すると良いでしょう。
• サイズの調整:お母さんと体型が異なる場合、着物の寸法を調整する必要があります。サイズ直しや仕立て直しをすることで、ぴったりのサイズに仕上がる場合があります。多少の寸法は着付けでもカバーができます。
• 現代的なアレンジ:お母さんの着物をそのまま着るのも素敵ですが、帯や小物を現代風にアレンジすると、より洗練された印象になります。
• 家族の思い出を共有:母から娘、娘から孫へと、着物が伝わることは家族の絆を深める素晴らしい経験です。写真に収めることで、3世代の物語を残すことができます。
5. 着物で迎える七五三、プロの力を借りることも選択肢
着物の準備に不安がある場合は、着付け師やリメイクのプロに相談するのも一つの方法です。専門家のサポートを受けることで、当日の流れがスムーズになりますし、安心して七五三を楽しむことができます。
まとめ
【受け継いだ着物】を楽しむためにおおよその目安で5ステップにまとめました。
七五三の準備は早めに開始:6ヶ月前からの準備がおすすめ
① 着物のサイズと状態確認:シミやサイズ調整が必要なら早めに手配、足りない物がないか確認
② 撮影・お参りの予約:2ヶ月前から準備を整え、予約を確定
③ 試着と確認:1ヶ月前に試着して最終確認を行い、当日安心
④ お母さんの着物を着る場合:サイズ調整や小物のアレンジで現代風に仕上げる
⑤ プロの力を借りる:着付けやリメイクの専門家に相談して安心
七五三の準備は、早めに計画を立てることで余裕を持って迎えることができます。受け継がれた着物を大切に扱い、家族みんなで思い出を作りながら、素敵な七五三を迎えてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございます。この記事が参考になれば嬉しいです。
着付け教室を開いています。ご質問等ございましたらお問い合わせください。
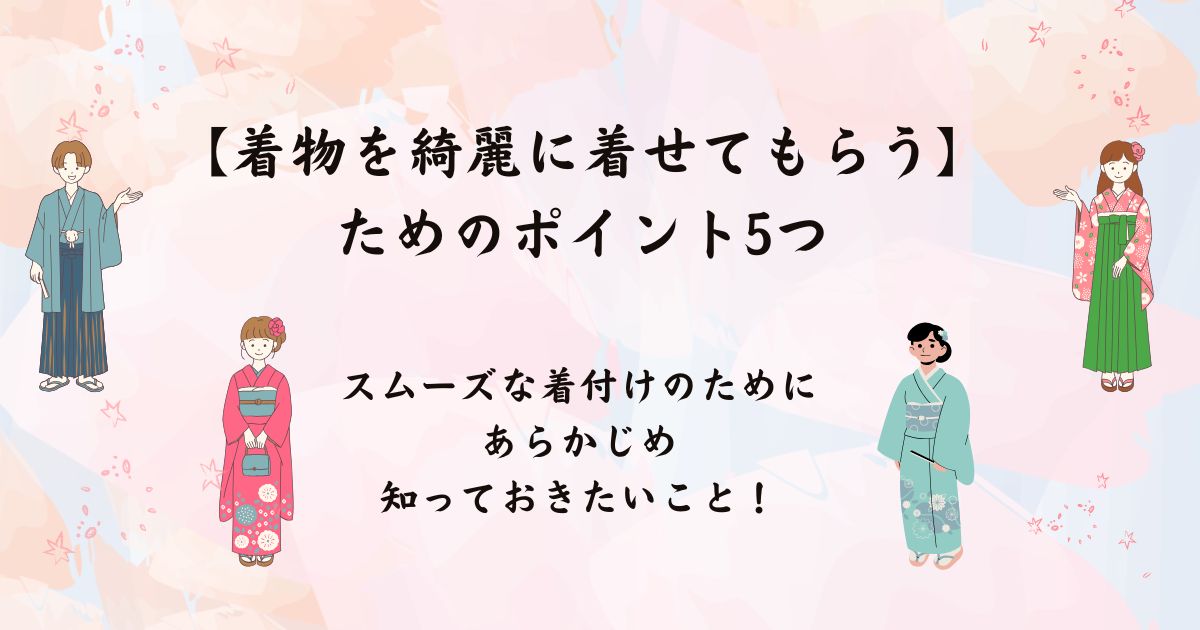
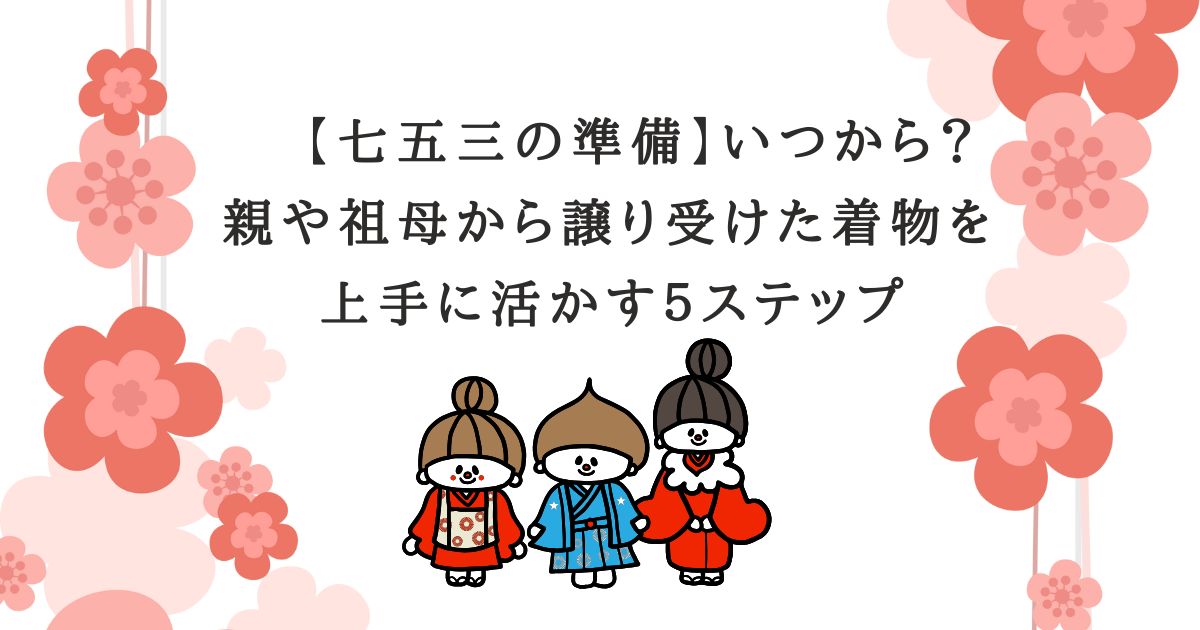
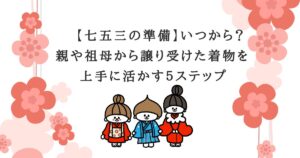


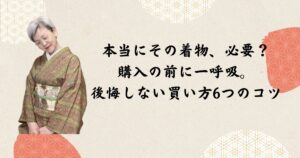
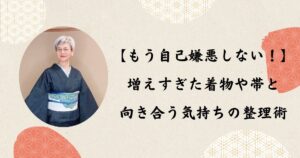
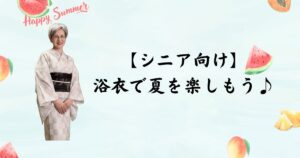
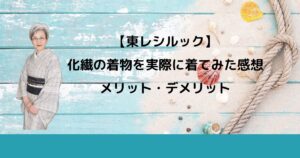
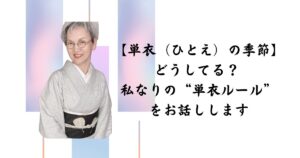
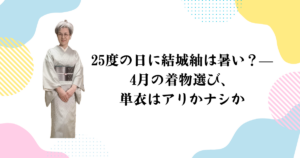
コメント