「着物をきれいに着たい」「着付けを始めてみたい」──そんな方に、まず知っていただきたいのが着物のサイズの大切さです。体に合わない着物や帯では、どんなに一生懸命練習しても上達しにくく、時間もお金もムダになってしまいます。
私は着付け講師時代、多くの生徒さんがサイズの合わないお母様の着物や、若い頃に作った着物で苦労している姿を見てきました。体型の変化や寸法の違いで、着付けが思うように決まらないのです。
そこで今回は、着付け上達に欠かせない3つの寸法と測り方、さらに合わない着物を活用する方法をわかりやすくお伝えします。
※「寸法」は専門用語ですが、「サイズのことです」
自分に合った寸法の着物と帯だと着付けが楽にきれいに仕上がります。

なぜサイズが大事なのか
洋服にS・M・Lといったサイズがあるように、着物にも細かな寸法があります。
着物のサイズが合っていないと、衿合わせやおはしょりがきれいに決まらず、着崩れの原因になります。
熟練者は多少の寸法違いを着付けの技術でカバーできますが、初心者の場合は自分に合ったサイズで練習することが上達の近道です。
着物サイズの基本「3つの寸法」
1. 身丈(みたけ)
- 着物の全体の長さ。
- 目安:自分の身長と同じ長さ。
- 合わないとおはしょりがきれいに決まりません。
2. 裄(ゆき)
- 首の後ろの骨(ぐりぐり)から肩を通り、手首の骨までの長さ。
- 洋服でいう袖丈に近いが、着物は背中心から測ります。
- 短いと手首が出すぎ、長いとだらしなく見えます。
3. 身幅(みはば)
- 着物の胴回り。
- 目安:ヒップサイズ+4cm。
- 足りないと歩くときにはだけやすく、大きすぎると巻き込んで歩きにくくなります。

ワンポイント:寸法はあくまで目安です。多少の誤差は問題ありません。ただし着付けがしにくいと感じたら、専門家に見てもらうと正確なサイズがわかります。
寸法の測り方のコツ
- 身丈:背中心(または肩)から裾までを測る。
- 裄:首の後ろの骨から肩を通り、手首の骨までを測る。
- 身幅:腰回りの一番太い部分(ヒップ)を基準に計算する。
換算に便利なのが鯨尺メジャー。片面が鯨尺、裏面がメートル表記で、相互換算が簡単です。
合わない着物は仕立て直しで活用
着物には仕立て直しという大きな特権があります。条件を満たせば、新しく買わなくても今ある着物を自分サイズに直すことができます。
仕立て直すときに、同時に自分の好みに合わせてアレンジすることもできます。
たとえば
- 八掛けの色を変える
- 単衣着物に仕立てる
- 年齢や好みに合わせて色を染め直す
といった調整が可能です。
ただし、反物の幅や長さが足りない、ヤケや針穴が残るなど、直せない場合もあるため専門家に確認してください。
また、費用もかかるので見積もりを取り検討してください。
私も姉の着物を深緑の八掛けに替えて仕立て直し、年齢を重ねても愛用できる一枚になりました。


サイズが合うメリット
- 着付けがスムーズになり、仕上がりが美しい
- 着崩れしにくくなる
- 練習の上達スピードが早まる
- 手持ちの着物の活用度が上がる
まとめ
- 初心者は「自分に合った寸法」の着物で練習するのが近道
- 特に身丈・裄・身幅の3つが基本
- サイズが合えば、時間もお金もムダにせず効率よく上達
- 合わない着物は仕立て直しで活用できる
- 基本をマスターすれば、多少の寸法違いは工夫でカバー可能
次のステップ
まずは自分の寸法を測り、手持ちの着物と比べてみましょう。ピッタリでなければ、仕立て直しを検討し着付けを始めると、効率よくきれいな着付けが身につきます。
母の夏紬を仕立て直し(身丈出し)して愛用しています。残布があったのがラッキーでした。

あわせて読みたい
さらに上達するために、帯のサイズ(長さ・柄出し位置)も確認しておくと、よりスムーズです。
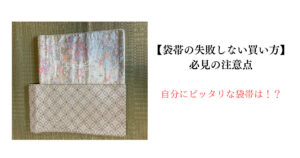
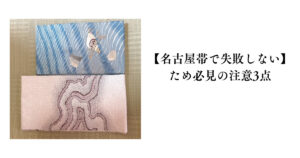
最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が参考になればうれしいです。
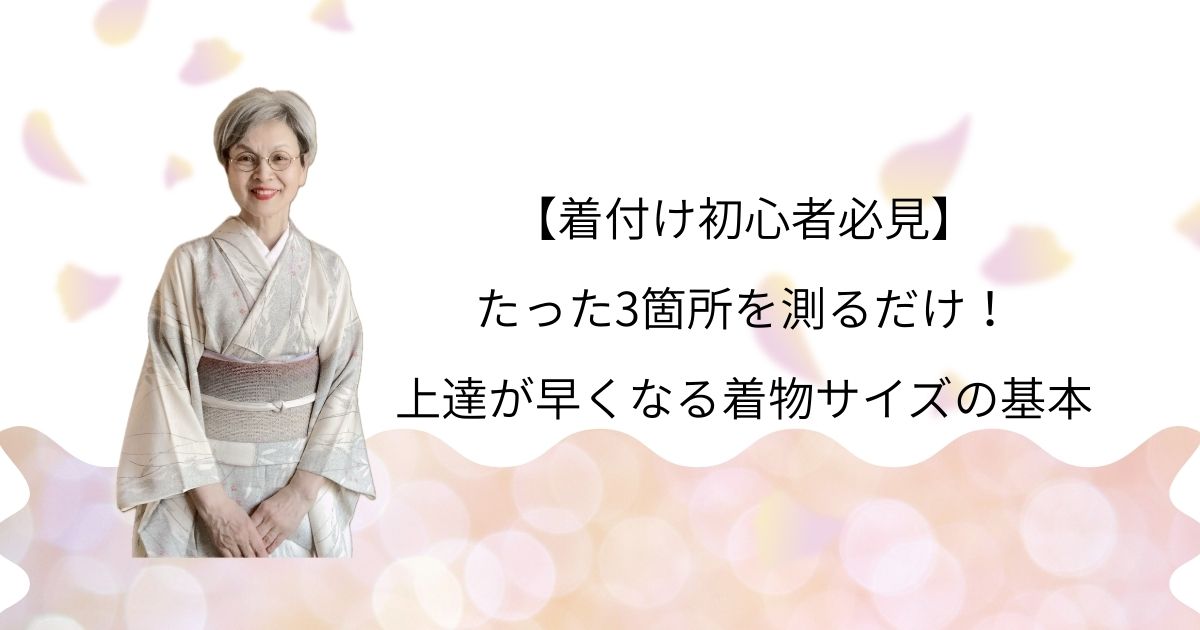
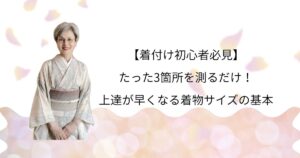

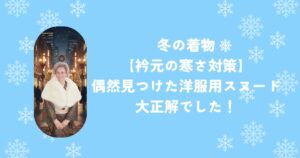
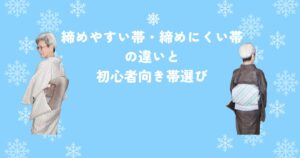
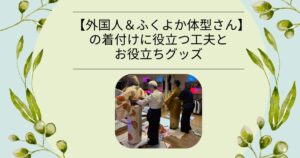
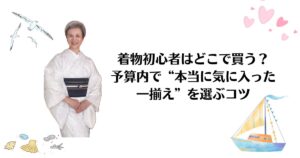
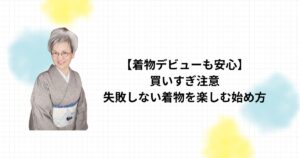
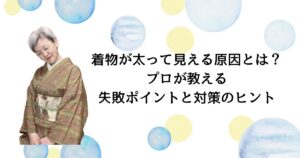

コメント